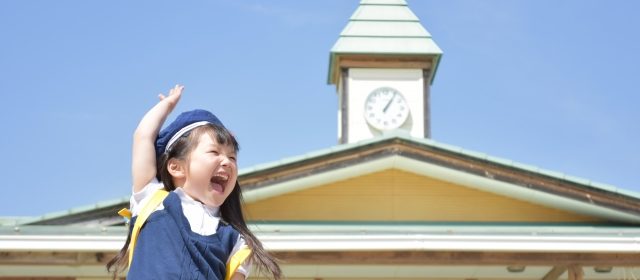働くママが多い今の時代は、子供を早くから保育園や幼稚園に預けるのが当たり前になりつつあります。
本来の入園年齢である3歳を待つママも多くいますが、0歳から預けるママも今では珍しくありません。
保育園の受け入れ可能年齢は?

保育園は0歳から入園可能です。
預けれる月齢は、自治体や保育園によって異なります。
最短では産休明けから預けられますが、4ヵ月、6ヵ月、11ヵ月以上など、保育園によって受け入れ可能な年齢が異なります。
東京都の世田谷区では、生後43日目から始まり、57日、5ヵ月、6ヵ月以上と受け入れ可能な月齢が細分化されています。
一時期、都市部の保育園は入園が困難で、待機児童が大勢いるとニュースで取り上げられた事があります。
その頃から「保活」という言葉が使われ始めましたが、今や保活は都市部だけではありません。
地方都市の保育園事情
私の居住地では、年度途中で公立保育園に入園させようと思うと、所在地にもよりますが、かなり難しいと言われています。
保育士の確保が難しいという状況もあり、0歳児は2名しか受け入れが出来ず、兄弟で同じ保育園に入園できない事も珍しくありません。
長男を出産した5年前は、0歳児から保育園に預ける親は少数派でしたが、共働き世帯の増加により保育園の需要が高まり、出産後早くから保活がはじまるようになりました。
幼稚園の受け入れ可能年齢は?
保育園とは異なり、年中から入園をして卒園まで在籍する2年保育と、年少から入園して卒園まで在籍する3年保育があります。
どちらを選択するかは、家庭事情や両親の考え方にもよりますので、どちらを選択するかは家庭によって異なります。
認定こども園
保育園や幼稚園のうち、一定の基準を満たした施設を都道府県知事が認定こども園として認定します。
子供に対して教育と保育園を一体的に提供し、子育て家庭に対する支援を行う施設です。
入園するための手続きは?

保育園、幼稚園、認定こども園のいずれの施設を希望するにしても、まずは世帯の就労状況に応じて支給認定を受けなければいけません。
認定は1号から3号まであり、2号と3号はそれぞれ8時間以内の短時間保育と、11時間以内の標準時間保育に分類されています。
認定結果に応じて、利用できる保育施設と利用可能時間が異なります。
入園するための申請書に支給認定の結果を記載して、各自治体の入園申し込み開始後に申し込みをします。
保育施設の選択は、よく話し合って決めよう

入園を考えるパパやママは、勉強を教えてもらいたいから幼稚園が良いとか、友達とたくさん遊んで欲しいから保育園がいいとか、どちらを選んだらいいか悩みますよね。
どちらも一長一短で、どちらが良いという訳ではありませんし、学童期にはどちらを卒園していてもほとんど差はありません。
子供は子供なりに、きちんと成長していくものです。
小学校に進学する時にも、なるべく保育園、幼稚園の友達が多い場所の方が環境の変化が少なくて良いのではないか・・・と親は考えてしまいがちです。
でも、子供は案外順応性が高く、環境に慣れる時間に個人差はあっても、きちんと新しい環境で友達を作り、新しい環境で学んでいきます。
子供の心配をしている親の方が、新しい環境に慣れるために時間がかかるかもしれません。
周りの意見は、参考程度に留めてOK
よく、「3歳までは親が育てた方がいい」と言う人がいます。
もちろん、実際3歳まで親が育てた方が良い部分があるのも事実です。
ですが、時代は移り変わるもので、その時の世の中の状況や家庭状況は流動的なものです。
自分の体験談ですが、5年前に6ヵ月だった長男を保育園に預けた時には、親族や近所からは苦情を言われました。
「まだ小さいのに可哀想」「3歳までは家でみるのが当たり前」
そんな風に言われる日々を過ごしてきましたが、長男は周りの子たちよりさまざまな面で発育が早く、保育園に預けていたからこその成長だと思います。
今は次男の保育園入園に奔走しているところですが、5年前とは違って0歳で子供を預けるママが多く、保育園探しが大変です。
この状況下では、誰も「まだ小さいのに可哀想」とは言いません。
子育てをしていると、外野から色々な事を言われますが、自分が信じるものを貫いて良いと思います。
だって、周りは口は出しても、実際に子供の面倒を見てはくれないのですから。
ママやパパの信念ある行動を見て育つ子供は、自分の考えをしっかり持つ子供になります。
子供はいつも親を見ているのです。
教育方針も、自分たちが良いと思うものを選択していって下さいね。